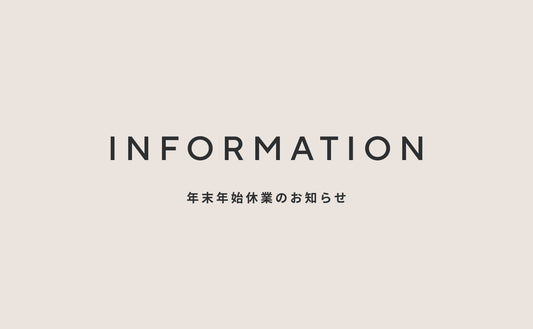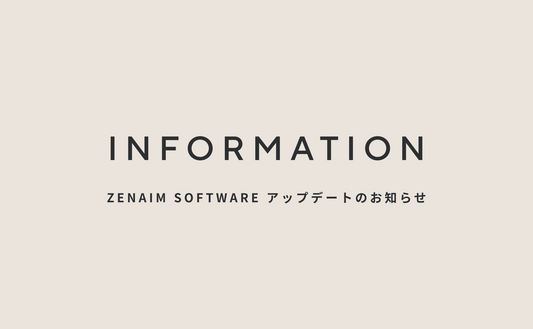1.ゲーミングキーボードの応答時間について(おさらい)
前回のコラム“ゲーミングキーボードの速さの秘密-応答時間を解剖する【前編】”では、磁気検知式キーボードを例に、ポーリングレートやスキャンレートといった仕様が応答時間にどう関わるかを整理しました。
応答時間とは、キーを押してから画面に結果が反映されるまでの一連の流れを指し、人間の動作を含めた総合的なレスポンスで決まります。
ZENAIMでは、ゲーミングキーボードに求める応答時間を、電気的な処理の時間に加え、キーをストロークさせる時間も含めた、総合的な応答時間を実用上の速さの指標として考えています。
今回はこの考え方を踏まえ、ZENAIM KEYBOARDがどのように応答時間を最適化しているのかを掘り下げていきます。

図1. ZENAIMの考える応答時間(再掲)
2.ZENAIMが追求した理想 ― 片手を安心して預けられるキーボード
ZENAIMが目指したのは、単純な「速さ」だけではありません。キー操作をする際のスムーズな指の動作をいかにサポートし、安定した入力を実現するかも同時に追求しています。速さ・正確さ・安定性が高い次元でバランスしたとき、デバイスとの一体感が得られると考えています。
プレイにおいて集中すべきはゲームそのものであり、キーボードは人とゲームを繋ぐためのデバイスであると考え、どのような操作体験ならばよりゲームに没入できるかを考えました。
突き詰めたのは、“片手を安心して預けられるキーボード”です。
ゲーミングキーボードにおける理想的な操作スタイルとしてZENAIMが前提としたのは、“しっかりと底打ちができること”でした。
接点を持たない磁気検知式キーボードは、アクチュエーションポイントもリセットポイントも自由に設定できることが強みであり、ラピッドトリガーはその強みを最大限に活かした機能であるといえます。理論上は、アクチュエーションポイントを最も浅く設定し、ラピッドトリガーのOFF設定を最短にすれば、最も速いON/OFF操作が可能になります。しかし、一般的なスイッチのストロークは通常3.5~4mm程度あり、最短操作を行うとキーの表面をなでるような動作が必要となります。
ここでは、この操作を”底打ち”に対し、“浮かせ打ち”と表現してみます。

図2. 底打ちと浮かせ打ち操作
浮かせ打ちは理論上最速になり得ます。実際に浮かせ打ちを巧みにコントロールするゲーマーも存在すると、海外を含めたゲーマーコミュニティの中で報告されています。
そのような中で、ZENAIMが底打ちを前提とした操作を推奨する根拠は以下の3点です。
指の動作精度を上げられる
指の操作には、”生理的ふらつき”があり、一般に0.01〜0.15mm程度の微小な揺れがあるといわれています。[1]
底打ちを前提とした操作では迷いなく指を押し下げることができるため、相対的に動作精度を上げることができます。
そのため、ZENAIMではキーは思い切って底まで打ち切ってしまったほうが結果的に入力が正確で速くなる、と考えています。
操作の素早さと安定性
底打ち操作では、ストロークの終わりに明確な振動が指へとフィードバックされます。物理的に終わりが定まることで、往復動作も素早く行うことができ、結果として安定したストロークを得ることができるようになります。[2]
また、前回のコラムでも言及したとおり、生体反応として触覚刺激は視覚や聴覚より速いため、底打ちの振動を感じてから次の動作までの時間は相対的に短くできる可能性が高いと考えています。[3]
疲労や注意負荷の低減
浮かせ打ちの場合、押し込みと戻りのストロークを指先で繊細にコントロールする必要があります。ゲームへの注意を払いながら継続的に正確な操作をするには高度な技術と集中力が必要とされます。入力に関する関連研究から、触覚による明確な刺激がある場合、対象に注意を傾けるための負荷が低下するという報告があります。[4]
このことから、底打ちを前提とした操作は指への明確なフィードバックを得られるため、浮かせ打ちに対して相対的にゲームへの集中を損なわせにくいと考えられます。
よって、浮かせ打ちは理論上最速といえますが、操作難易度は高い。底打ちは安定性と再現性が高く、連続的な操作に強い、といえます。以上の理由から、ZENAIMでは精度の高い操作を長時間維持するには底打ち操作が有効である、と考えています。
では、底打ちを前提とした操作において、ZENAIMがキーボードに求めたものは何だったのでしょうか?
1.誤爆と応答速度のトレードオフ解消
ストロークを短くすれば入力は速くなりますが、その一方で誤爆のリスクが高まります。ZENAIMはトッププロゲーマーとの共創により、応答時間の短さと誤爆のしにくさの両立する最適解を追求しました。独自開発した、1.9mmという超ショートストロークのZENAIM KEY SWITCHがスムーズな入力操作をサポートします。
(参考:ZENAIM KEY SWITCH)
2.タッチインフォメーションの実装
“タッチインフォメーション”とはZENAIM独自の造語です。
これは、車のドライバーがアクセルやブレーキのペダル越しに路面状況を感じ取る際に用いる“ロードインフォメーション”に着想を得たものです。
前述のとおり、触覚は視覚よりも速く脳に認識されるため、キーを押し込んだとき指先から得られる微細な触覚情報は、次の操作をより素早く導くことができると考え、しっかりとキーを底まで押し込んだとわかる打鍵感を作りこみました。
3.ストレスのない操作感
押下とリリースで荷重差がなく、スムーズにまっすぐ沈むストローク。これにより直感的かつ一体感のある操作体験を提供し、プレイヤーの集中力をゲーム内の重要なイベントに傾けられるようにサポートします。
これらを突き詰めることで、ZENAIMは“片手を安心して預けられるキーボード”を目指しました。
では、ZENAIM KEYBOARDの実用上の応答時間はどの程度なのでしょうか?
3.応答時間の計測と評価
最初に、総合的な応答時間を計測するため、人間がキーを連続打鍵する際の運動についてモデル化を行いました。
既存研究を調査しつつ、FPSゲームで移動キー(WASD)を操作する際の指の置き方や標準的な連打の速度を割り出し、専用設備にプログラミングしました。一般的なノーマルプロファイルのスイッチは3.5㎜~4mm程度のストロークを持っています。これらのスイッチを素早くかつ無理なく操作できる打鍵の周期について、文献値をもとに200ミリ秒(0.2秒)と仮定し、その往復動作の速度を設備で再現させました。[5]
また、WASDキーの操作では指をキートップから大きく離さずに打鍵を繰り返すことが多いため、ストローク時の空振り距離をなくし、実用上の動作を再現することに主眼を置いた設備の設定をしています。
計測対象としたのは以下の3つのフェーズです。
- キーを完全にリリースした状態から ON判定 まで
- ON判定から OFF判定 まで
- OFF判定から キー完全リリース まで
ストローク動作と時間、ラピッドトリガーのON/OFF判定の関係を図3に示します

図3. 計測条件
この条件を前提に、他社ラピッドトリガーキーボードとZENAIM KEYBOARDの応答時間を計測しました。
比較対象としたA社キーボードについて、センシング~演算処理の実際の所要時間やデッドゾーンの実効値は非公開で、完全同一には揃えきれません。そこで本試験ではラピッドトリガーのON/OFF・デッドゾーンの設定を表1のとおり共通化し、同一の操作速度で繰り返し計測をし、結果を比較しました。

表1. 比較対象キーボード
この条件でZENAIM KEYBOARDと他社キーボードを比較した結果が図4になります。

図4. 計測結果
結果まとめ
この計測結果をまとめると以下のように説明できます。
- キー完全リリースからON判定の時間は同等
- OFFまでの時間は、超ショートストローク設計によりZENAIMが明確に短い
- キー完全リリース状態からONし、底打ち後にOFF判定するまでの差は約34ミリ秒(0.034秒)
- 完全リリース状態までの時間差は約80ミリ秒(0.08秒)
ストローク3.5mmのキーを200ミリ秒の周期、つまり1秒に5回程度打鍵できるスピードでZENAIM KEYBOARDを操作した場合、底打ちまでの時間が短くなり、結果的にON~OFF、完全リリースから再度ONするまでの時間を短くできることがわかります。
考察
結果のグラフをよく見ると、キーを押しこむ時間と戻る時間が半分ずつにならず、非対称であるように思えるかもしれません。キーの完全リリースから底打ちになるまでと、そこから再び完全リリースするまでの時間は、速度が一定であれば同じ時間になるはずですが、現実の往復運動では、押し込み時の加速度、底打ちによる減速、スイッチの摩擦や動作のゆらぎ等が影響し、きれいに対称になりません。
また、ZENAIM KEYBOARDをA社キーボードと同じスピードで操作する場合、ストロークが短いぶんピーク速度に達するまでの加速度が必然的に速くなるため、完全リリース~ONまでの移動時間が相対的に短くなります。
デッドゾーンの実効値の不確かさに加え、この移動時間の差があることで、ポーリングレートとスキャンレートによる電気的な遅延の差が埋まり、ほぼ同じON判定時間となっていると考えられます。
本結果から、ON→OFFが短い=底打ちからの切り返しが早い、OFF→完全リリースも短い=次の入力に素早く復帰ができるといえます。つまり底打ち操作を前提とした場合、ショートストロークはストッピングも連打も安定的に速い、という強みがあるといえます。
4.考え抜かれた超ショートストロークの強みと今後の展望
前回のコラムからここまでで、磁気検知式キーボードの仕組みやゲーミングキーボードの応答時間を構成する要素を紐解き、人の動作を含めた実用上の応答時間について詳細に触れてきました。
ZENAIM KEYBOARDのロープロファイル・超ショートストロークは、直感的な操作と人間の感覚に寄り添った速さを両立するために生まれた設計です。
応答時間の9割は人間側——だからこそZENAIMは人に寄り添う設計を重視しています。
この思想は現在開発中のアーケードコントローラのボタンにも受け継がれています。
製品の用途ごとに最適解を模索し続けていますので、これからリリースされる製品を楽しみにしていただけると嬉しいです。
また、今後はさらに応答時間を突き詰めたキーボードの開発も予定しています。
これまでも、これからも、ZENAIMが大切にしているのは“何がユーザーにとってのWELLなのか?”という問いかけです。
あなたのプレイを支えるために、ZENAIMは“WELL GAMING”を追求し続けます。
参考文献:
[1] E. Z. Ahronovich, N. Simaan, and K. M. Joos, “A review of robotic and OCT-aided systems for vitreoretinal surgery,” Advances in Therapy, vol. 38, no. 5, pp. 2114–2129, 2021
[2] J. R. Kim and H. Z. Tan, “A study of touch typing performance with keyclick feedback,” in Proc. IEEE Haptics Symp. (HAPTICS), 2014, pp. 227–233.
[3] A. W. Y. Ng and A. H. S. Chan, “Finger response times to visual, auditory and tactile modality stimuli,” in Proc. Int. MultiConf. Eng. Comput. Sci. (IMECS), vol. II, 2012.
[4] Z. Ma, D. Edge, L. Findlater, and H. Z. Tan, “Haptic keyclick feedback improves typing speed and reduces typing errors on a flat keyboard,” in Proc. IEEE World Haptics Conf. (WHC), 2015, pp. 220–227.
[5]Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. The Keystroke-Level Model for User Performance Time with Interactive Systems. Communications of the ACM, vol. 23, no. 7, pp. 396–410, 1980.